おはこんばんにちは!スーダスです。
今回は私にしては珍しく、仕事で使える報告資料の作成テクニックを紹介してみたいと思います。
目的
世の迷える会社員たち(特に製造・開発関係の方々)が少しでも早く仕事を終わらせて、少しでも早く帰れる一助になれば!との思いで書いてみました。
もし、ご意見やアドバイス、ここがもうちょっと知りたい、私はこうやってる、などあればコメント頂けますと幸いです。
課題
仕事で皆さんが業務報告したり、承認をもらいに行くとき、こんなことで困っていないでしょうか?
上司に業務報告を出しても内容が伝わらない。
権限を持っている部署に承認を得にいってもなかなか理解されない
上司に「やりたいことは分かったけど、どうしてコレやりたいの?」と言われてしまう
このようなことで悩んでいる方は、この記事をもう少し読んでみてください。
原因
何故このような悩みが尽きないのでしょう?(´・ω・`)
その原因は、あなたが書きたいことを書いているから、あるいはあなたが「やること」にフォーカスして書いているからです。
しかし、受け取り手は、何故それをやるのか?、それをやると何が良くなるのか?もセットであなたから報告されないと判断や助言ができません。
対応
それでは、どうしたら伝わるようになるでしょうか?
簡単です。
この記事の見出しの順で報告してみてください。つまり、
- (目的)
- 課題(QCDのうち1つ)
- 原因
- 対応
- 今後(日程)
の順です。
それではそれぞれの項目についてもう少し細かく説明します。
目的
まず、その報告で何をしたいのか?つまり、目的を明確にしましょう。
単なる報告・情報共有なのか?承認が欲しいのか?方向性を相談したいのか?を考えて示してください。
日報・週報などある程度目的が決まっている報告については書かなくても構いません。
課題
仕事とは「困りごと解決」です。
あなたのやりたいことは、「困りごと=課題」を解決することのはずです。
では「課題」とは何でしょう?
私はよくこんなことを言われます。
品質が担保できないのが課題だし、納期に間に合わないのも課題だし、お金がかかるのも課題だし、あれもこれも課題です。
本当にー?
確かに業務上の課題は色々あります。そして、それらは密接に関係し、一見複雑に絡み合い、すべてが課題のように見えます。
そんな時は、落ち着いて「何が本当の課題なのか?」を整理してみてください。
複数の課題に因果関係がないか?をなぜなぜしてみたり、物事を時系列順に並べてみたりして、本当の課題を特定してみてください。
すると課題は以下の3つのうちどれかに当てはまります。
Q:品質課題
1つ目は品質課題です。開発業務の方は技術課題と読み替えていただいて差支えありません。
世に出すための品質目標を達成できない、技術的解決がない場合はこの課題です。
これが課題である場合、目標の見直しを検討する、販売をやめるなどの判断が必要になります。
C:費用課題
2つ目は費用課題です。
これは大きく分けて「単価」と「投資」への影響があります。
もっと言ってしまえば課題になるのは「単価上昇」と「追加投資」です。
「単価上昇」は同じ製品を作り続ける限り、ずっと反映されますので、会社収益へ影響してきます。
「追加投資」は1度だけなので、同じ製品を作り続ければ影響は薄まっていきます。ただ、変動が大きすぎればプロジェクトに影響しかねません。何年で何個作ると何円/個の影響があるなど、長期的な目線での判断も必要になります。明示していきましょう。
D:日程課題
基本的には納期です。
ただし、単純なモノの納入日程だけでなく、法律に規制されているモノであれば認可の日程も考慮する必要があります。
また、各プロセスが日程表(ガントチャート)で分かるようにしておくと、解決策が見えてきます。
原因
課題が設定出来たら原因を調べてみましょー。
原因は目に見えることが本当の原因とは限りません。
巷でよく言われている「なぜなぜ」をやって、真因を探してみてください。
※なぜなぜのやり方については言及しません。YouTubeやネット記事などでいろいろなやり方を紹介していると思うので参考にしてください。
対応
真因が分かったら、どうしたら解決できるか考えてみましょー。
そうすると、
- 今の方法・技術では対策しきれません。
- お金を〇〇円使わせてください。
- 対策を〇〇日ほしいので、納期遅らせてくださいor先行で取り組ませてください
というような結論が出てくると思います。
これが報告事項で一番伝えたいことですね?
また、真因に手を打つだけでは解決できないことも多々あります。
例えば、「発売直前に判明した部品の強度不足」という課題の真因が、「担当者の見落とし」だった場合、
真因への対策は、「見落としを防ぐ仕組みづくり」です。
しかし、仕組みだけ手当てしても目の前にある部品の強度不足はどーすんねん?という話になります。
両方やりましょう。
ただ、同時にやるのは難しいと思いますので優先順位を決めて取り組んでください。
今後(日程)
最後は今後の対応日程の話です。
日報・週報では、単純な期日だけでよいと思います。できるだけ具体的な期日が好ましいですが、方向性を決めるだけにならざるを得ないこともあるでしょう。
パワポなど資料を使った報告であれば、日程表(ガントチャート)で示してください。視覚的にどのようなプロセスを踏んでいくのか、現時点どういう状況なのかが分かりやすいです。相手の理解を助けるだけでなく、自分自身にも状況が分かり易くなるので、自分のためにもやってください。
今後
今回ご紹介したやり方は日常の報告業務で割と何でも使えるんじゃないかなーと思っています。
しかし、日々忙しく仕事をしている中では、いざ書こうというときに思い出せないこともあるかと思います。
もし、報告用のフォーマットがあるのなら、そのフォーマットに本記事の5項目をあらかじめ書いちゃいましょう(・∀・)
- (目的)
- 課題(QCDのうち1つ)
- 原因
- 対応
- 今後(日程)
このように書いておけば、あらかじめ何を書くかが決まっているので、抜け漏れなく書くことができます。中身は皆さんで考えて書いてもらうしかないんで、それはそれで頑張ってくださいw
初めのうちは全部かけなくてもいいと思います。発生したばかりの課題は原因究明が終わってなかったり、解決策が見えてなかったりするのは普通です。そういうときは、どういうことをやろうとしているか?いつまでにやろうとしているか?を書いておきましょう。
大事なことは、課題解決に向けて今後必要なことを認識して行動することです。
では、この記事を読んでくれた方の仕事が少しでも楽になることを祈って(-人-)
いじょ。

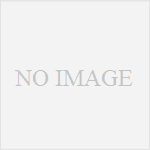

コメント